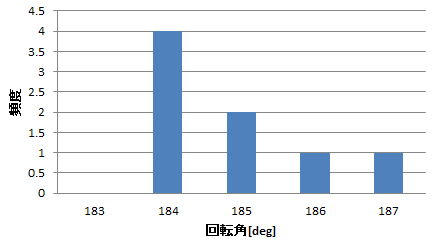現在、世の中にある多くのものが「インスタント化」する傾向を持っていると私は考えている。例えば一昔前にはネットで情報を公開するためには、ユーザが自らHTMLファイルを作成しサーバーにアップロードする必要があったが、それが簡単に投稿可能なBlogというシステムに置き換えられ、更に最近ではそのBlogもフェイスブックやTwitterにその座を奪われつつある。この流れの本質は「簡易さ」と言える。
現在、世の中にある多くのものが「インスタント化」する傾向を持っていると私は考えている。例えば一昔前にはネットで情報を公開するためには、ユーザが自らHTMLファイルを作成しサーバーにアップロードする必要があったが、それが簡単に投稿可能なBlogというシステムに置き換えられ、更に最近ではそのBlogもフェイスブックやTwitterにその座を奪われつつある。この流れの本質は「簡易さ」と言える。これと同様の変化がゲーム業界でも起こっている。資金と手間をかけた大作のゲームが、チープなソーシャルゲームに敗北するという現象が起きている。この理由も明快で、「手軽」だからだと考えられる。スマートフォンが普及しただとか、コンシューマ機のソフトが複雑化・高コスト化し過ぎただとかいろいろな議論はあるが、突き詰めれば「簡易さ」に負けたというところに集約されるだろう。
これは忙しい現代人に対して需要と供給が成り立ったという意味では、何ら問題はなく適切に進化したのだと捉えることもできるが、私はこれにより一つ重要な問題が起きるということを主張したい。
すなわち、現代人は一つの物事に対してじっくり取り組む機会が奪われており、これは人の成長において著しい悪影響になりうる、ということである。
勉強でもゲームでもそうだが、一つのことを極めようと努力すると、その過程で試行錯誤した経験により、新たな分野(この場合は新しい教科・学問領域、あるいはゲームとか)にチャレンジしようとした際の理解速度は随分違う。直感的には、基礎能力が同程度という条件下で数学をすごい頑張った人とそうでない人とでは、経済学を学ぼうとした時の習得速度に大きな差が生まれるだろうという予想から、この主張の妥当性を考えることができるだろう。
だから思春期には、よく悩みよく考えて、何かに打ち込むことがやはり必要だと思われるのだが、社会で供給される娯楽がことごとく「インスタント化」されているとその機会は失われがちになるのは間違いない。
それでも、チープな中にも奥深さを見出すのが若者のたくましさでもあるが(いわゆるクソゲーでもきっと幼いころはそれなりに楽しめたはずだ)、元々の作りの底が浅ければ、やはり限界は早く訪れるだろう。
なので私は、思春期を超えるまでの間は子供にスマートフォン(その時には死語になっていそうだが)を自由に使わせないつもりでいる。
自己コメント: 何分文献等がないため、説得力に欠けます。また、色々細かいことを説明するのが面倒になったので、文脈がかなり強引です。この手の記事2個めということで大目に見てください。